わたしの娘たちがオーストラリアの公立小学校に通い始めて早数年。日本では考えられないような指導方法やイベントが盛りだくさんで、「こんなのでいいのだろうか……。」と母親としてモヤモヤする毎日です。
今回は、日本人には理解しがたい、オーストラリアの小学校事情をご紹介します。
オーストラリアの小学校は「先生」というよりも「友達」

日本では、小中高の先生はもちろん、保育園の先生や習い事の先生も「○○先生」と呼ぶ習慣があります。たとえその先生が自分より年下であっても、保護者も子供と同様「○○先生」と呼びますよね。
しかし、オーストラリアでは、保護者はもちろん、子供にも「トム」や「ケイト」という風にファーストネームで呼ばせる先生も少なくはないんです(Mr/Miss/Mrs○○(○○先生)と呼ばせる先生も多いです)。
わたしの長女と次女が通った幼稚園では、園児との「友達のようなカジュアルな関係」を好む先生が多く、2人とも担任の先生はファーストネームで呼んでいました。
日本人のわたしとしては、先生を友達のようにファーストネームで呼ぶなんて考えられないので、娘たちには「Hello, Miss○○」と挨拶するように促していました。しかし、ある日先生に「そんなにかしこまらなくていいのよ」と言われてしまったのです。
かといって、「カジュアルなスタイルを好む先生たちは適当な指導をするのか?」といえば、そういうことはなく、教育者としての資格だけではなく、児童心理学にも詳しい、非常に勉強熱心な先生方なんです。
日本のように、必ず「○○先生」と呼んで敬意を表す習慣も素晴らしいとは思いますが、形だけではなく、「生徒や保護者との信頼関係」を重視するカジュアルな関係も悪くはない、と感じる今日この頃です。
【よく読まれる人気記事】
オーストラリアの小学校に存在しない「時間割り」

日本の学校では、「月曜日の1時間目は国語、2時間目は算数……」というふうに、毎日の「時間割り」というものが存在します。
オーストラリアでは、「1時間目は何時から何時まで。ランチは何時から……」や「水曜の午後は体育の時間」という大まかなスケジュールは決まっていますが、日本のようなきっちりした時間割はありません。
「何曜日の何時から、何を勉強するか」というのは、すべて「担任の気分次第」で決まります。
「時間割がない」という教育方針になれず、長女が小学校に通い始めたころは、学校での様子を把握するのに苦労しました。かといって、何も勉強していない、ということはなく、日本の小学校よりも、かなりゆっくりなペースで勉強しているようです。
また、日本の学校と違い、大勢の前で自分の考えを自信を持って表現する「プレゼンテーション能力」に力を入れているようです。幼稚園のころから「Show and tell」という、家族写真や自分で書いた絵、お気に入りの本などをクラスの前で発表する時間を設けています。
時間割がない、けじめのなさそうな教育ですが、日本の学校教育ではあまり重視されていない「自己表現の力」を重視しているのは、オーストラリア教育のいいところなのかもしれません。
小学校の宿題はすべてオンライン
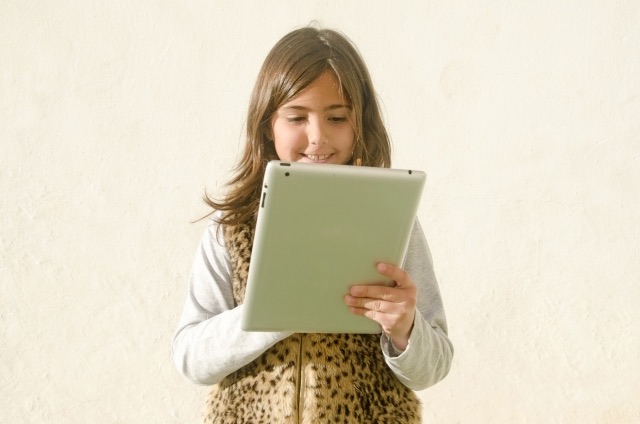
わたしが小学生だったころは、インターネットもない時代でしたので、宿題はすべて「ノートと鉛筆」でした。最近の日本の学校でも、コンピューターなどを大いに取り入れているのだと想像します。
オーストラリアの学校でも、授業でコンピューターを大いに利用するのですが、宿題もすべてオンラインです。担任の先生から「宿題用ホームページのIDとパスワード」をもらって帰ってきて、親のパソコンからログインし、各自宿題をします。
そこで気になるのが、「家にパソコンがない子や、親の帰りが遅くてパソコンを使えない子たちは、どうやって宿題をしているのだろうか?」ということです。娘の話によると、現にクラスの中に「お母さんが仕事でパソコンを使うので、宿題ができません」という子も数人いるそうです。
コンピューターやインターネットは非常に便利なツールではありますが、幼いころからそればかりに頼ってしまうのは、少し疑問に思います。「宿題の基本はノートと鉛筆から!」という考えは、もう時代遅れなのでしょうか……。
「親のため」のクラスイベント

毎年クラスには「Social Rep(Representative:「代表」の意)」という役目の保護者が一人います。学年の始まりに立候補し決定します。毎学期ごとに、学校外でのクラスのお遊び会の計画を立て、学年の終わりには、担任の先生のお別れ会とお礼のプレゼントを準備するのが、「Social Rep」の役割です。
毎学期、「クラスのお遊び会」の連絡メールが「Social Rep」から届くたび、疑問に思うことがあります。それは、必ず、以下のような一文が書かれていること―
「You are welcome to bring adult oriented refreshments. There is nothing like a beer or wine to kick off the weekend!」
(ビールやワインなどもお持ちください。楽しい週末を始めましょう!)
学校外ではあるものの、なぜ子供のためのイベントに、大人がお酒を飲む必要があるのでしょうか?
実際に、お遊び会に行ってみると、子供たちは自由に遊び、保護者達はビールを片手に世間話をし、子供たちがどこにいて、どのような遊びをしているのか、全く把握していない状況なんです。
お友達のお誕生日会にお呼ばれしても同様に、子供は勝手にケーキを食べて遊び、保護者はビール片手に世間話をしているんです。
わたしには、どう考えても、「子供たち同士の交流を深めるため」というのは見せかけだけで、ただ保護者が集まって、お酒を片手に愚痴を言い合いたいだけのイベントにしか見えません。それは、ただ単にわたしが日本人だからなのでしょうか……。
まとめ
いかがでしたか?
良く言えば「ゆとりのある教育」、悪く言えば「けじめのない」オーストラリアの学校事情をご紹介しました。
わたしの娘たちには、オーストラリアの教育の良いところも吸収させつつ、日本の教育の素晴らしい面も教えられるといいな、と思っています。
海外求人
【採用担当者の方】海外就職希望者への新しい求人広告(無料キャンペーン中)
あなたの挑戦を待っている!あこがれの海外企業へ就職しよう(海外求人)
おすすめ
オーストラリアのブリスベンで観光も楽しむ!上手な休日の過ごし方
 台湾
台湾 韓国
韓国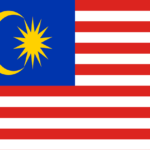 マレーシア
マレーシア インドネシア
インドネシア タイ
タイ インド
インド イギリス
イギリス ドイツ
ドイツ アメリカ
アメリカ カナダ
カナダ

![Guanxi Times [海外転職]](https://wakuwork.jp/wp-content/uploads/2023/05/type3.jpg)








